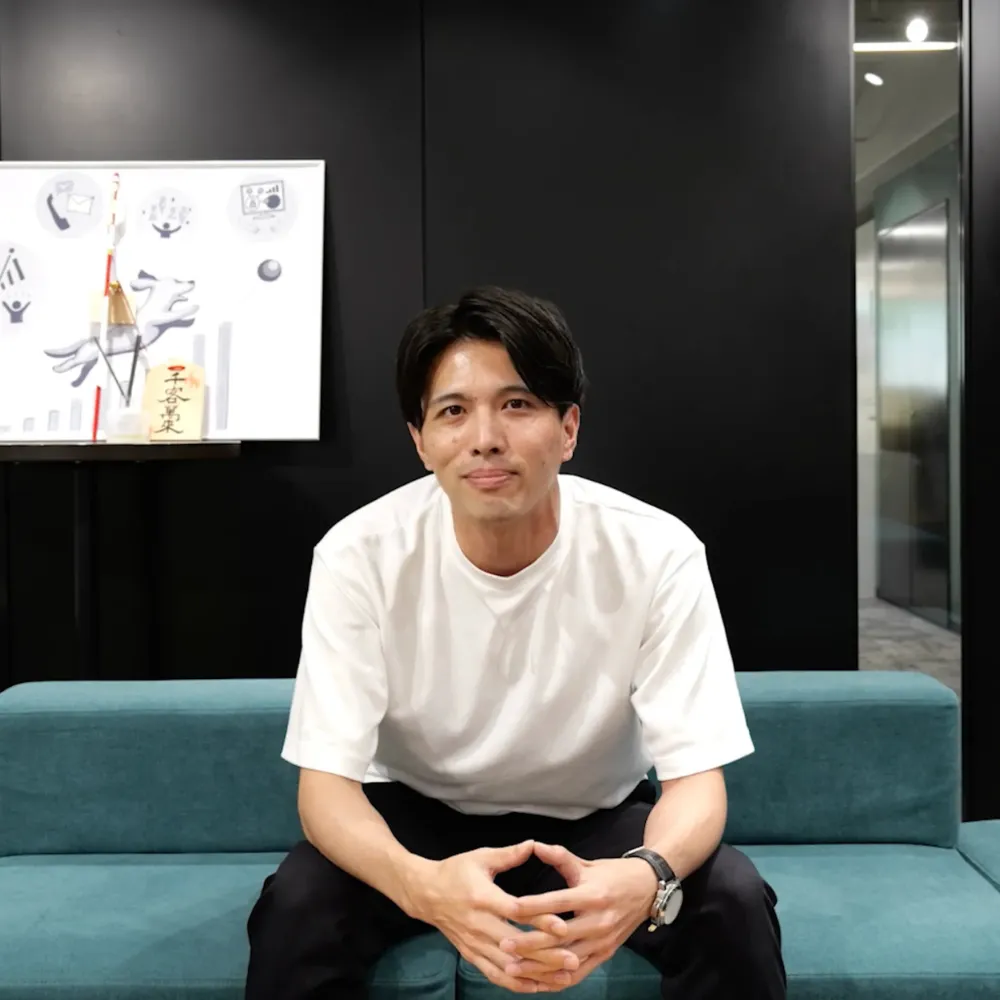製造業で新規事業を立ち上げる際に、「技術力はあるが営業力が足りない」という壁にぶつかった経験はありませんか?
本記事では、アズビル株式会社が「現場でつくる作業記録サービス」の拡販において、わずか3カ月で商談数を約10倍、受注数を4倍に伸ばした営業改革の実例をご紹介します。
エンジニア主体の組織が直面した新規事業の壁
アズビル株式会社は、100年以上の歴史を誇る計測制御機器の大手メーカーです。同社が開発した「現場でつくる作業記録サービス」は、製造現場の紙ベースの作業記録をデジタル化する画期的なソリューションでした。技術的には優れた製品でしたが、大きな課題を抱えていました。
「正直なところ、営業できる人材がいなかったんです」
伊藤常務は当時の状況をこう振り返ります。もともと縮小を検討していた事業であったこともあり、新規に営業人員を配置する意思決定が難しい状況でした。展示会やWebサイトからの問い合わせといったインバウンド中心の営業活動では、トライアルまでは進むものの、本契約に至るケースは限定的でした。
同社はこの課題を解決するため、1,500万円を投じてコンサルティング会社に支援を依頼。市場での立ち位置や強みを分析した資料は完成しました。しかし伊藤常務は苦笑いを浮かべながら語ります。
「立派な分析資料はできました。でも、それを実行に移すリソースがなければ意味がない。情報はあっても、実際に動けなかったのが現実でした」
なぜアズビルはDigiManを選んだのか
転機は意外な形で訪れました。DigiManからアズビルへの営業アプローチがきっかけでした。
「最初は普通の営業電話だと思っていました」と伊藤常務。しかし、DigiManの提案は他社とは明らかに異なっていました。単なる営業代行ではなく、「事業戦略を立て、営業の立案から実行、商談を含めて実行する」という提案に、伊藤常務は強い関心を示しました。
「コンサルタントに『こうすべきだ』と言われても、実際にはできないことが多い。でもDigiManさんは、私たちができない部分をともに汗を流しながらやってくれる。これが決め手でした」
特に価値を感じたのは、営業戦略の立案から実行までを一貫してサポートする点でした。さらに、キーエンスの営業手法を熟知したメンバーが在籍している点も、エンジニア主体のアズビルにとって大きな魅力でした。
「今のエンジニアに営業をやれと言うのは現実的ではありません。餅は餅屋。営業のプロフェッショナルに任せるべきだと判断しました」
3カ月で成果を出したDigiManの営業代行アプローチ
現場理解から始まる勝ちパターンの発見
DigiManのプロジェクトは、徹底的な現場理解から始まりました。営業担当の菊池氏は、アズビルの湘南工場を訪問。実際に「現場でつくる作業記録サービス」がどのように使われているかを自分の目で確認しました。
「製造現場を実際に見ることで、このサービスの真の価値が理解できました。単なる紙のデジタル化ではなく、品質管理の効率化や作業ミスの削減にもつながる。この価値を正確に伝えることが重要だと確信しました」(DigiMan 菊池氏)
さらに、既存顧客の工場も訪問し、アンケートを通じて利用者の生の声を収集。これらの情報を基に、成功事例の要素を分解し、同じ課題を抱える他の企業に展開する「ヨコ展開戦略」を構築しました。
データドリブンなリスト作成と架電戦略
次にDigiManが着手したのは、効率的なアウトバウンド営業の仕組み作りでした。過去の受注履歴を詳細に分析し、「熱いアポの方程式」を導き出しました。
熱いアポ=規模×業種×部署×役職×同席人数
特に重要視したのは「業種」と「部署」の組み合わせでした。組み立て加工業の品質管理部門など、セグメントごとにアプローチ方法を最適化。さらに、各セグメントの歩留まりを細かく管理することで、どの領域に注力すべきかが明確になりました。
架電においても明確なKPIを設定。1時間あたり15件の架電を基準とし、アポ率3%を目標に設定。結果として、600件の架電で20件のアポイントを獲得する体制を確立しました。
キーエンス流「EFAB」を活用した商談設計
商談においても、DigiManは独自のメソッドを導入しました。それが、キーエンス流の「EFAB」アプローチです。
・E(Empathy/共感):製造現場の課題への深い理解と共感
・F(Function/機能):課題を解決する具体的な機能の説明
・A(Advantage/優位性):競合製品と比較した優位点
・B(Benefit/価値):導入により得られる具体的な成果
「以前は機能説明ばかりしていました。でも、お客様が本当に知りたいのは『この製品で何が変わるのか』ということ。EFABの順番で伝えることで、お客様の反応が明らかに変わりました」(伊藤常務)
商談では役割分担も明確化。ファシリテーションとクロージングはDigiManの菊池氏が担当し、技術的な詳細説明はアズビルが担当。この連携により、商談の質が大幅に向上しました。
驚異的な成果:インバウンド依存からの脱却
わずか3カ月のプロジェクト期間で、アズビルの営業成果は劇的に改善しました。
【Before】
- 商談件数:2〜3件/月(インバウンドのみ)
- トライアル転換:限定的
- 営業活動:受動的な問い合わせ対応のみ
【After】
- 商談件数:20件/月(コンスタントに実現)
- トライアル件数:12件(3カ月累計)
- 受注件数:4件(3カ月累計)
- 営業活動:能動的なアウトバウンド中心
「数字以上に大きかったのは、勝ちパターンが見えたことです。工業会、取引先リスト、組み立て加工業など、どのセグメントにアプローチすれば良いか、どう伝えれば響くのか。これが明確になったことで、今後の営業戦略に確信が持てるようになりました」(伊藤常務)
製造業DXにおける営業改革の3つのポイント
アズビルの事例から、製造業がDX製品の営業で成功するための3つのポイントが見えてきます。
1. 現場理解の重要性
製品の機能ではなく、現場でどのような価値を生み出すかを理解することが不可欠です。DigiManが工場訪問を重視したのも、この現場理解があってこそ適切な価値提案ができるからです。
2. データに基づいた営業戦略
勘や経験だけでなく、過去の実績データを分析し、科学的にアプローチすることで効率的な営業活動が可能になります。セグメントごとの歩留まり管理は、限られたリソースを最大限活用するために欠かせません。
3. 専門性の活用
エンジニアには開発に集中してもらい、営業は営業のプロに任せる。この役割分担が、新規事業の成功確率を高めます。内製化にこだわらず、外部の専門性を活用する柔軟性が重要です。
まとめ:エンジニア企業こそ営業代行を活用すべき理由
アズビルの事例は、技術力の高い製造業が新規事業で直面する典型的な課題と、その解決策を示しています。優れた製品があっても、それを適切に市場に届ける営業力がなければ、ビジネスとしては成立しません。
「エンジニアは製品開発に集中し、営業はプロに任せる。この割り切りができたことが、今回の成功につながりました。分析だけでなく、実際に手を動かしてくれるパートナーの存在が、我々には必要でした」(伊藤常務)
製造業のDX推進において、営業力の強化は避けて通れない課題です。しかし、それを全て内製化する必要はありません。むしろ、外部の専門性を活用することで、より早く、より確実に成果を出すことができるのです。